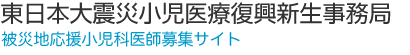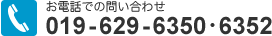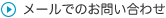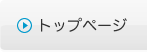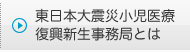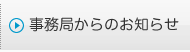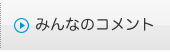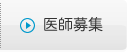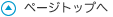事務局からのお知らせ
特別寄稿 岩手医科大学医学部小児科学講座 教授 小山耕太郎 先生
東日本大震災小児医療復興新生支援事業へのお礼のことば
東日本大震災からまもなく10年が経とうとしています。この間、全国の皆様から多くの温かいご支援をいただきましたことに厚くお礼申し上げます。日本小児科学会、日本小児救急医学会におかれましては、東日本大震災小児医療復興新生事務局を通して、全国の小児科医の皆様に被災地における診療応援を募集していただき、心より感謝申し申し上げます。被害がとくに甚大であった気仙地域の県立大船渡病院と高田病院、内陸の遠野病院、胆沢病院、磐井病院にはこれまで多くの先生から応援をいただきました。あらためてお礼申し上げます。
東日本大震災津波は、岩手県では、2020年1月現在、死者4,674名、不明者1,112名、そして多数の関連死をもたらしました。県内の被災地は災害復興道路の整備が進むとともに大規模なかさ上げ工事が終わり、予定されていたすべての災害公営住宅が完成しました。しかし、宅地整備の遅れや工事の順番待ちなどからまだプレハブに暮らす住民もおり、震災の風化がいわれるなかで、生活やコミュニティーの再建はむしろこれからというのが実情です。また、こころのケアや子育て支援が必要な子ども、家族も多くみられます。一方で、震災の経験や教訓を将来に伝承しようとする子どもたちが現れているのは大きな希望です。
県内各医療圏はもともと医師不足に悩んでいましたが、とくに被災地は、地理的な特徴から医療圏が孤立しやすく、支援が困難です。まだまだ苦難の続く被災地の住民にとって、小児科医の確保は、地域で生きる支えのひとつであると思います。今後とも皆様の応援をお願い申し上げます。
令和3年1月25日
岩手医科大学医学部小児科学講座
小山 耕太郎
特別寄稿 阿部こどもクリニック 院長 阿部淳一郎 先生(石巻市)
2021年3月であの日から10年を迎えます。石巻市では多くの方が亡くなりました。
あの当時の地元新聞を見返しました。死亡者名簿が掲載されて、患者さんの名前を確認したときの気持ちは忘れられません。信じたくないけれども、載っている。あの住所なら、それもあると認識。悲しい記事の連続でした。他には、給水がどこで行われる、食事の配布があります、入浴がどこそこでできます。仙台までの数本のバスの時間。生活に必要なことが掲載されました。やがて、時間とともに記事は普通に戻っていきました。
石巻赤十字病院の小児科は2000年代に入るまでは、常勤医師2名と非常勤医師1−2名で、相対的に開業医の役割は大きいものでした。夜間診療は当たり前ですが、週末の医療も在宅当番医が主でした。しかし、ニーズをフルカバーできず、2002年5月から平日夜間診療を夜間急患センターに移し、石巻市医師会小児科医と隣接医師会の小児科医、そして内科医の協力を得て開始。なんとか継続させて頂いたところに、東日本大震災を経験。その後、震災を契機に宮城県小児科医会、東北大学小児科、石巻赤十字病院小児科と、東日本大震災小児医療復興新生事務局のお力添えでの派遣医師のご支援で維持されております。今後も、開業医の個の力から基幹病院や全国的な小児科医のご支援に軸を移していければ、小児科医が不足する地方都市でも小児医療が継続されます。コロナウイルスの流行で、地方都市での生活のメリットが再認識されます。そのときに必要な要素の一つは、医療の提供だと思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。
阿部こどもクリニック
阿部淳一郎
特別寄稿 福島県立医科大学小児科 教授 細矢光亮 先生
2011年3月11日の東日本大震災から間もなく10年が経ちます。福島県では、日本小児救急医学会「東日本大震災小児医療復興新生事務局」を通じて、全国のたくさんの方々より、県内の3つの病院に対して温かいご支援を頂いております。
福島県太平洋沿岸部の相馬双葉地区にある公立相馬病院は、地震、津波、原発事故で大きな被害を受けましたが、この地区で唯一の小児入院機能を堅守しています。中通り中部にある公立岩瀬病院は、常時20-40名の小児入院患者があり、2017年4月には周産期医療を担う新病棟がオープンして周産期・新生児医療も始まり、県中地域の小児科診療拠点の一つに成長しています。超過疎地域の南会津地方にある県立南会津病院は、他の医療圏からは遠く離れており、たった1人の小児科医がこの地域の小児医療を担っています。
お蔭様で、一旦崩壊しかけた福島県の小児医療体制は、ようやく回復に向かっております。これからも、「ほそくながく」ご支援をお願いします。
福島県立医科大学小児科 細矢光亮
特別寄稿「ほそくながく」日本小児救急医学会 副理事長 米倉竹夫 先生
2011年3月11日に発生した東日本大震災は、地震・津波・放射線災害という未曽有のtriple disasterで、岩手・宮城・福島3県を中心に甚大な被害をもたらしました。日本小児救急医学会では3月18日から54日間にわたり陸前高田市に小児救急の医師派遣を行い、私もこれに参加しました。目の当たりにした陸前高田市の被災状況や岩手県立高田病院の石木院長やスタッフの皆さんと一緒に過ごした時間を、今でも忘れることができません。
東日本大震災の教訓をもとに、日本小児科学会、日本小児科医会、日本小児保健協会、日本小児期外科系関連学会協議会からなる日本小児医療保健協議会では、領域横断的な小児周産期災害医療支援活動を目的に、2015年4月に小児周産期災害医療対策委員会を立ち上げました。その後、災害時小児周産期リエゾンが設立され、熊本地震以降の小児周産期領域の災害医療支援活動に繋がっています。
災害マネジメントサイクルの災害発生後のフェーズには発災直後から復興が含まれます。東日本大震災小児医療復興新生事務局による小児医療支援(医師派遣)事業は、被災地の小児医療の復興支援として、被災地域の未来を担う子どもたちのために貢献していくものと考えます。これからも「ほそくながく」の趣旨にご賛同の先生方のご支援を心よりお願いします。
一般社団法人 日本小児救急医学会 副理事長
日本小児医療保健協議会 小児・周産期災害医療対策委員会 委員長
近畿大学奈良病院 小児外科 教授
米倉竹夫
特別寄稿「震災後10年を迎えて思うこと」 公立相馬総合病院小児科 伊藤正樹
午後の外来中に突然の大きな揺れが発生しました。
その後は津波に原発事故と、立て続けに今まで経験したことのない事が起こり、その都度多くの方々のご支援、ご助言を頂き今日に至ります。
災害は続くもので、台風による水害で相馬市内全域が断水したこともありました。そして、現在のコロナの流行など、災害はいつやってくるか本当に分かりません。常に備えることが大切だと痛感しております。
当院は本事業を通じて全国各地から大勢の小児科の先生に支援を頂きました。
この十年で、地震、津波被害を受けた沿岸部はかなり整備され、復興に向けて確実に前へ進んでおります。
当時赤ちゃんだったお子さんも、今は小学校高学年。当科を受診するお子さんの多くが震災後に生まれた子供たちになってきました。
震災後も以前と変わらぬ小児科医療を提供しようと努めてまいりましたが、今日まで続けてこられたのも、多くの支援の先生方のお陰だと本当に感謝しております。
震災当時のことを知らない子ども達が増えてきましたが、ここ相双地域には依然として、放射能による居住困難区域が存在し、処理水の海洋放出の問題、そして燃料デブリの取り出しや廃炉に関することなど、多くの現在進行形の問題を抱えています。
元通りになることは難しいと思いますが、今の状況の中で、子供たちが健やかに暮らして行けるよう出来る限りの医療を提供していきたいと思っています。
これまでのご支援に深く感謝させて頂くとともに、今後も変わらぬご支援、ご助言を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
公立相馬総合病院小児科 伊藤正樹