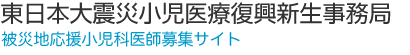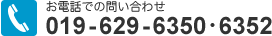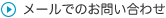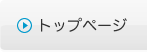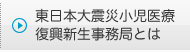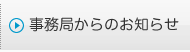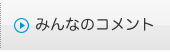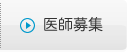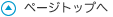みんなのコメント[岩手県立大船渡病院]
「ほそく、でも、ながい」お手伝い上田 一仁(所属:名古屋大学小児科(前 公立陶生病院))
2014/03/14
[岩手県立大船渡病院]
2013年8月、東日本大震災小児医療復興新生事務局のお力を得て、私は初めて震災後の岩手県を訪れさせて頂きました。
2011年3月当時、初期研修医であった自分は、「何かしたい」と思いながらも、勤務先の病院が派遣した医療チームを応援することしか出来ませんでした。その後、小児医療に携わる中、この事業のことを知り、夏季休暇を利用して応募させて頂きました。
震災前後を通じて岩手県を訪れたのは初めてでしたが、そこで目にしたものは私の想像を遥かに超えていました。震災と津波の未だ消えない傷跡、あの日のことを無言で伝える震災遺構、未だ十分とは言えない復興状況… そこには、岩手山をはじめとする美しい自然とはあまりにも裏腹な現実が横たわっているように思いました。
しかしその一方で、大船渡、陸前高田、遠野の各病院で懸命に働かれている先生方の姿に接し、深い感動を覚えました。また、2011年のあの時、全国から集った医師が時間を共にした小屋の壁には、熱いメッセージがびっしりと書かれていました。同時に診療の合間には病院のスタッフの方々からも手厚いお心づかいを頂き、岩手の方々の温かさをしみじみと感じました。
こうした光景は、愛知に帰った今も忘れることが出来ません。そんな自分に少なくとも今できることは伝えることだと思い、訪問時の写真を時折見せながら、この事業のことを周囲に紹介したりしています。
季節柄患者数も少なく、また1日体調を崩してしまったこともあり、今回自分が「支援させて頂いた」などとは決して申し上げられません。むしろこれからも、自分にできる「ほそく、でも、ながい」お手伝いの機会を伺っていこうと思います。私の心に、色々なものを頂いた本事業に、改めて感謝申し上げます、ありがとうございました。

2011年3月当時、初期研修医であった自分は、「何かしたい」と思いながらも、勤務先の病院が派遣した医療チームを応援することしか出来ませんでした。その後、小児医療に携わる中、この事業のことを知り、夏季休暇を利用して応募させて頂きました。
震災前後を通じて岩手県を訪れたのは初めてでしたが、そこで目にしたものは私の想像を遥かに超えていました。震災と津波の未だ消えない傷跡、あの日のことを無言で伝える震災遺構、未だ十分とは言えない復興状況… そこには、岩手山をはじめとする美しい自然とはあまりにも裏腹な現実が横たわっているように思いました。
しかしその一方で、大船渡、陸前高田、遠野の各病院で懸命に働かれている先生方の姿に接し、深い感動を覚えました。また、2011年のあの時、全国から集った医師が時間を共にした小屋の壁には、熱いメッセージがびっしりと書かれていました。同時に診療の合間には病院のスタッフの方々からも手厚いお心づかいを頂き、岩手の方々の温かさをしみじみと感じました。
こうした光景は、愛知に帰った今も忘れることが出来ません。そんな自分に少なくとも今できることは伝えることだと思い、訪問時の写真を時折見せながら、この事業のことを周囲に紹介したりしています。
季節柄患者数も少なく、また1日体調を崩してしまったこともあり、今回自分が「支援させて頂いた」などとは決して申し上げられません。むしろこれからも、自分にできる「ほそく、でも、ながい」お手伝いの機会を伺っていこうと思います。私の心に、色々なものを頂いた本事業に、改めて感謝申し上げます、ありがとうございました。

東北から日本全土へ井上 真紀(所属:大分大学医学部小児科)
2014/01/09
[岩手県立大船渡病院]
この度、東日本大震災から遠く離れた九州の大分から、大船渡病院と陸前高田病院へ東北診療応援に参加させていただきました。
初めて訪れた大船渡市・陸前高田市は、想像していたよりも復興はすすんでおらず、いまだに震災の傷跡が生々しく残っている印象を受けました。多くの方が仮設住宅に住み、仕事も少なく、利便性の悪い環境を目の当たりにし、震災から3年近く経った今もこの生活を続けている方々の苦労は計り知れないものと感じました。実際に仮設住宅にもお邪魔させていただきましたが、12月でも床や壁から冷気が伝わり、とても寒々しかったです。
私が支援に行ったのは3泊4日でした。2年以上経った被災地で、この短期間にできたことはほんの少しの日常診療だけです。東北診療応援を現地での活動量だけで測るなら、私の行ったことはとても些細であり、意味がないと言われればそうかもしれません。ただ、私が被災地に行って得たことは非常に多く、実際に行かなければ感じ得ないことばかりでした。まず一つは被災地の現状、人々の思いや復興の経過について身をもって知りえたこと、もう一つは被災地が中心となって広がる各県の医療者を含めた人々の輪とつながりを持てたことです。
大分に戻った後は今回経験できた全てを出来る限りの人々と共有することはもちろん、被災地を中心とした小児医療の輪から大分県に足りないものを吸収し、また大分県の優れたところを被災地を通じて日本全土に発信していくことが必要だと感じました。私の力だけでは微力ですが、多くの方が東北に訪れて同様の経験をすることで、被災地を中心とした輪が広がっていき、被災地だけでなく日本中の医療が発展していけると考えています。

初めて訪れた大船渡市・陸前高田市は、想像していたよりも復興はすすんでおらず、いまだに震災の傷跡が生々しく残っている印象を受けました。多くの方が仮設住宅に住み、仕事も少なく、利便性の悪い環境を目の当たりにし、震災から3年近く経った今もこの生活を続けている方々の苦労は計り知れないものと感じました。実際に仮設住宅にもお邪魔させていただきましたが、12月でも床や壁から冷気が伝わり、とても寒々しかったです。
私が支援に行ったのは3泊4日でした。2年以上経った被災地で、この短期間にできたことはほんの少しの日常診療だけです。東北診療応援を現地での活動量だけで測るなら、私の行ったことはとても些細であり、意味がないと言われればそうかもしれません。ただ、私が被災地に行って得たことは非常に多く、実際に行かなければ感じ得ないことばかりでした。まず一つは被災地の現状、人々の思いや復興の経過について身をもって知りえたこと、もう一つは被災地が中心となって広がる各県の医療者を含めた人々の輪とつながりを持てたことです。
大分に戻った後は今回経験できた全てを出来る限りの人々と共有することはもちろん、被災地を中心とした小児医療の輪から大分県に足りないものを吸収し、また大分県の優れたところを被災地を通じて日本全土に発信していくことが必要だと感じました。私の力だけでは微力ですが、多くの方が東北に訪れて同様の経験をすることで、被災地を中心とした輪が広がっていき、被災地だけでなく日本中の医療が発展していけると考えています。

新地に立つ - adovocate(代弁者) -野村 理(所属:東京都立小児総合医療センター 救命救急科)
2013/12/23
[岩手県立大船渡病院]
12月16日、17日の2日間、大船渡病院、高田病院での診療支援の機会を頂きました。
東北出身でありながら震災後ずっと支援に伺うことができず、今回ようやく願いを叶えることができました。
大船渡、陸前高田の旧市街地の新地(さらち)に立つと、ここにたくさんの家庭があり、それぞれが生活を営み、
こどもたちが育っていたということは理解していても、やはり想像できない、受け止めきれないという感情を抱きました。だからといって東北を出ている自分に何ができるわけでもない無力感は途方もなく募るわけでした。
そんな中でも、2つの病院の先生方やスタッフの方々が困難に対峙しながら、そこに居続け
笑顔でこども達を見守る姿はまさにadvocate(代弁者)でした。
そして、こども達は、診察室で大きな声で挨拶をしてくれ、大きな口をあけて診察に応じてくれます。
この子たちがあの新地(さらち)に新しい家、家庭、生活、街、地域を作っていくのだと思うと「普通」の一般小児科外来、予防接種が別の意味を持つように思え、感じたことのない充実感のようなものに包まれました。
このような素敵な機会を頂けたこと、先生方、スタッフの方々、こども達、ご家族の皆様に感謝申し上げます。
今後も何度でも伺えればと存じます。この度は本当にありがとうございました。
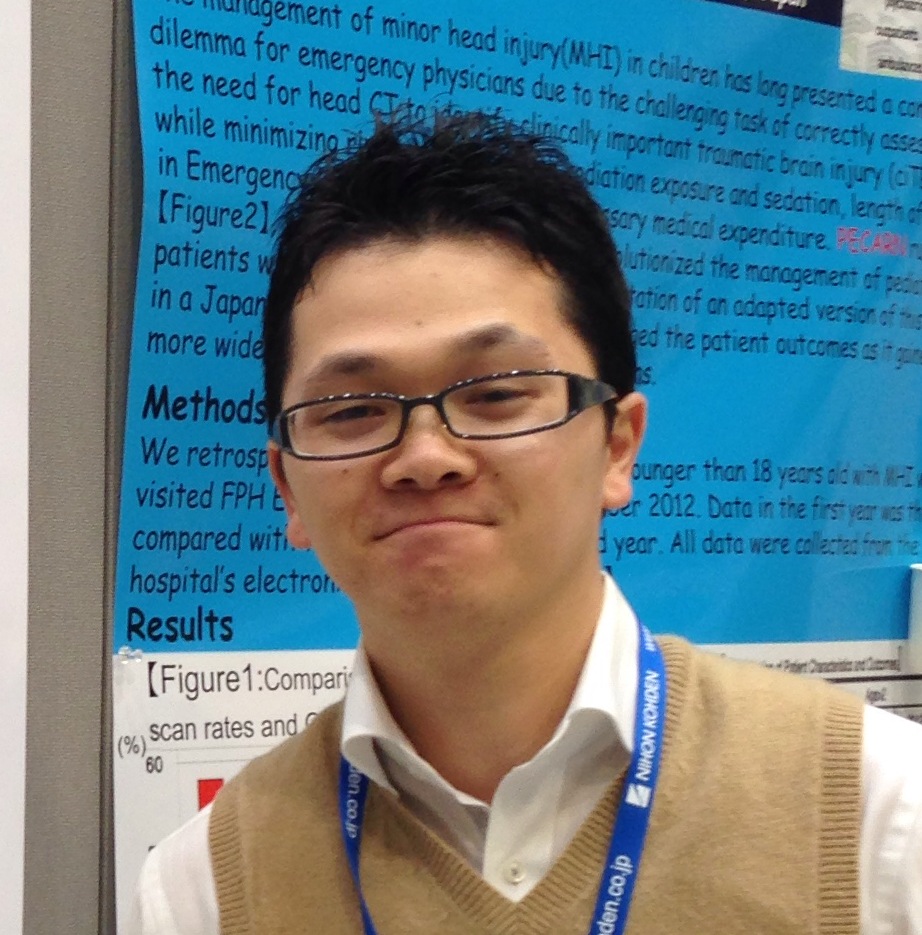
東北出身でありながら震災後ずっと支援に伺うことができず、今回ようやく願いを叶えることができました。
大船渡、陸前高田の旧市街地の新地(さらち)に立つと、ここにたくさんの家庭があり、それぞれが生活を営み、
こどもたちが育っていたということは理解していても、やはり想像できない、受け止めきれないという感情を抱きました。だからといって東北を出ている自分に何ができるわけでもない無力感は途方もなく募るわけでした。
そんな中でも、2つの病院の先生方やスタッフの方々が困難に対峙しながら、そこに居続け
笑顔でこども達を見守る姿はまさにadvocate(代弁者)でした。
そして、こども達は、診察室で大きな声で挨拶をしてくれ、大きな口をあけて診察に応じてくれます。
この子たちがあの新地(さらち)に新しい家、家庭、生活、街、地域を作っていくのだと思うと「普通」の一般小児科外来、予防接種が別の意味を持つように思え、感じたことのない充実感のようなものに包まれました。
このような素敵な機会を頂けたこと、先生方、スタッフの方々、こども達、ご家族の皆様に感謝申し上げます。
今後も何度でも伺えればと存じます。この度は本当にありがとうございました。
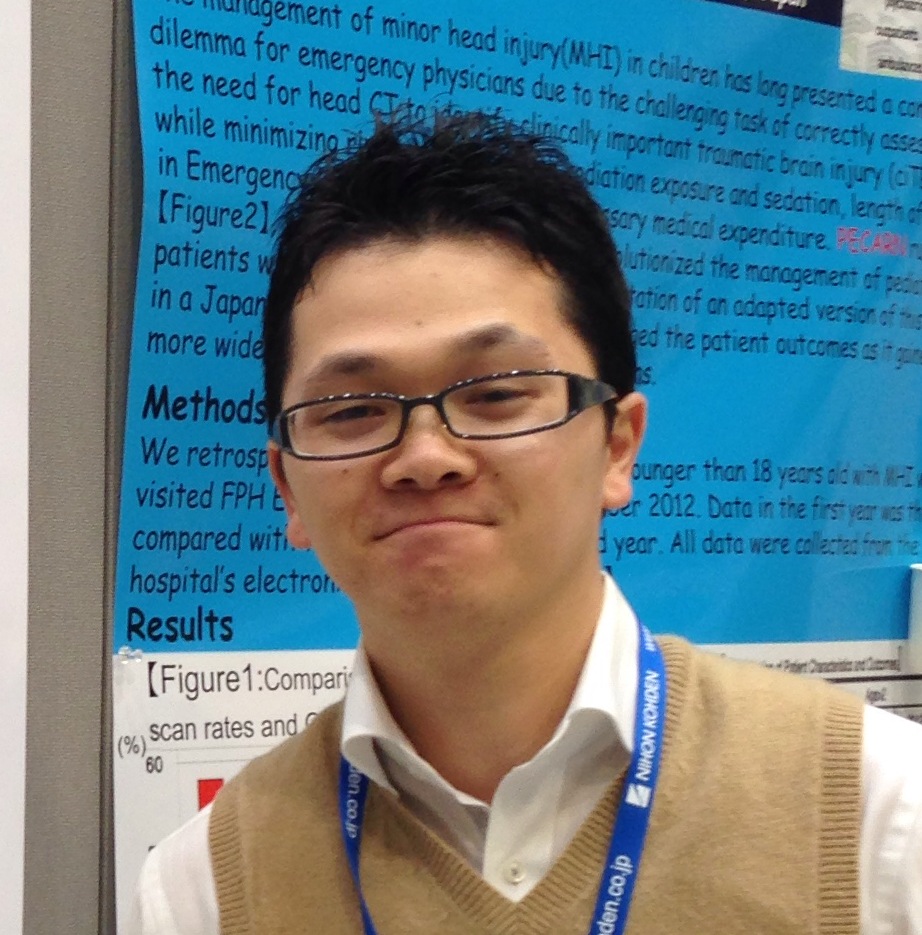
楽天優勝と笑顔豊福 明和(所属:横浜労災病院 小児科)
2013/12/19
[岩手県立大船渡病院]
小児科学会のHPを見ていたと ころ、東日本震災小児医療復興新生児事務局のHPにたどりつきました。
HPを見ると、1週間や1ヶ月などの期間でなく、数日の単位 でも被災地応援に行けることを知ることができました。
数日間でも何かできるのだと思い、3連休に大船渡病院に行かせていただきました。
電子カルテの使い方など色々教えてくださった、先生方、スタッフの方々、本当にありがとうございました。
震災当時のまま残っている建物を見たり、当時のお話を聞かせていただくことは、とても辛かったですが、
現状を少しですが知ることができたと思います。
小学校の校庭には仮設住宅があり、その片隅で子どもたちが集まっていました。
これからも、この子どもたちを少しでも笑顔にできるお手伝いができればと思いました。
ちょうど楽天優勝の時でしたので、皆さんの笑顔がみれて嬉しかったです。
ぜひ、また行かせていただければと思います。

HPを見ると、1週間や1ヶ月などの期間でなく、数日の単位 でも被災地応援に行けることを知ることができました。
数日間でも何かできるのだと思い、3連休に大船渡病院に行かせていただきました。
電子カルテの使い方など色々教えてくださった、先生方、スタッフの方々、本当にありがとうございました。
震災当時のまま残っている建物を見たり、当時のお話を聞かせていただくことは、とても辛かったですが、
現状を少しですが知ることができたと思います。
小学校の校庭には仮設住宅があり、その片隅で子どもたちが集まっていました。
これからも、この子どもたちを少しでも笑顔にできるお手伝いができればと思いました。
ちょうど楽天優勝の時でしたので、皆さんの笑顔がみれて嬉しかったです。
ぜひ、また行かせていただければと思います。

大海の一滴川野 達也(所属:大分大学医学部小児科)
2013/11/16
[岩手県立大船渡病院]
平成25年3月から小児科学会の支援事業および当科教授の指示により、毎月の岩手県気仙地区(大船渡市、陸前高田市)への定期診療応援が始まり、8回目の今回、10月23日~26日まで大船渡市に来させていただきました。
ここに来るまでは、実質2日半の支援で自分に何が出来るのか、非常に疑問に感じでいました。
大震災から2年半が経過した今でも、復興とは程遠い現状を目の当たりにし、とても衝撃を受け目の前が涙でかすみました。被災地の今を身を持って実感できたことは、私にとって大きな意識改革につながりました。医療支援の初めの一歩として、被災地や小児医療の状況を身をもって知っただけでも、意義があることと思いました。
私達の支援は、大海のたった一滴の水に過ぎないのかもしれません。でもその一滴の水が集まって大海になるのだという思いを新たにしました。出来ることは限られていますが、それでも自分達に出来ることをコツコツと続けて行きたいと強く思うようになりました。これから被災地の先生方や地域の方々に貢献するには何をすべきか考え続けて行きたいと思います。是非、今後も継続し、本当の意味での医療支援につなげていきたいと思います。当地の小児医療の発展を願ってやみません。
このような機会を与えていただき、本当にありがとうございました。

ここに来るまでは、実質2日半の支援で自分に何が出来るのか、非常に疑問に感じでいました。
大震災から2年半が経過した今でも、復興とは程遠い現状を目の当たりにし、とても衝撃を受け目の前が涙でかすみました。被災地の今を身を持って実感できたことは、私にとって大きな意識改革につながりました。医療支援の初めの一歩として、被災地や小児医療の状況を身をもって知っただけでも、意義があることと思いました。
私達の支援は、大海のたった一滴の水に過ぎないのかもしれません。でもその一滴の水が集まって大海になるのだという思いを新たにしました。出来ることは限られていますが、それでも自分達に出来ることをコツコツと続けて行きたいと強く思うようになりました。これから被災地の先生方や地域の方々に貢献するには何をすべきか考え続けて行きたいと思います。是非、今後も継続し、本当の意味での医療支援につなげていきたいと思います。当地の小児医療の発展を願ってやみません。
このような機会を与えていただき、本当にありがとうございました。